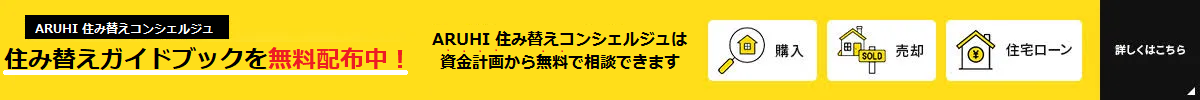「スイス漆喰ってなに?」
突然、窓の外を眺めていた彼女が質問をしてきた。僕は面食らって「え?」と返すので精一杯。
「だってこの壁、スイス漆喰なんでしょ?」
白い壁を触りながら彼女が言った。
「し、漆喰っていうのは、建築材料のことで、日本と西洋とじゃ、成分が違うんだけど――」
咄嗟の僕の説明に、木製サッシの窓から外を眺めている彼女がふむふむと頷く。
「す、スイス漆喰っていうのは、不純物の少ない石灰石が原料で、普通は1400℃の高温で焼くんだけど、スイス漆喰は950℃の低温で1週間かけて焼くんだって。で、そもそもスイスには『バウビオロギー』っていう概念があって――」
そこまで僕が言い掛けると、彼女がハッと振り向いた。「ずいぶん詳しいのね」と驚くような態度で。ところが、僕がスマートフォンで知識のカンニングをしていたことが分かると、彼女は「な~んだ」と落胆するような素振りをみせ、再び背中を向けてしまった。いくら建築学部の僕だって、咄嗟にスイス漆喰が何かなんて、スマートフォンで調べなければ人に説明なんか出来っこない。
僕が弱りながら「ば、バウビオロギーていうのは、健康な住まいを求める新たな学問、建築生物学とか生態学って意味で、 環境意識の高いスイスやドイツなんかで――」と続けても、彼女はもはや興味なし。やがて「別に聞いてない」とそっけなく言って、キッチンのほうへ行ってしまった。
僕もソファから立ち上がって、追うように彼女のほうへ。といっても2メートルの縛りがあるから、僕は食卓で立ち止まって、四人掛けの木製テーブルに立ったまま寄りかかった。
すると彼女が唐突に冷蔵庫を開けた。「なにも入ってないでしょ」と僕が言うと、彼女は「まぁね」と答えてすぐに閉めた。
「いつもなに食べてんの?」
続けざまに彼女が訊いてきた。
「ひ、一人暮らしだから、米を炊いて、チャーハンとか、炒め物が多いかな」
キッチンカウンターの手触りを確かめながら、彼女は「ふ~ん」と僕に返した。
ほとんど対面しているとはいえ、彼女は僕と目を合わせなかった。彼女は天井から下りて来るように設置されている換気扇に興味を示したのか、自分の背丈と比べるような手振りをみせた。
そこから妙な沈黙が流れた。彼女も落ち着きが無かったが、僕だって内心はそわそわしていた。2メートルの距離があるとはいえ、付き合ってもいない若い男女が、家の中で向かい合っているのだ。
「なに考えてるの?」
不意にこちらの考えを見透かしたように彼女が訊いてきた。
「い、いや、別に……」
こちらの曖昧な回答によって再び沈黙が訪れる。僕はこの時、漠然と、彼女と同じことを考えていると思った。「もし、私たちが付き合ったら――」「もし、この家で同棲したら――」「もし――」と。
そういう、荒ぶる気持ちが抑えられなくなった僕は、ええいままよと勇気を振り絞って、彼女に言った。
「ロフトに、行こうか」
「え」
彼女は小さく掠れた声で答えた。
「ロフトに、行こう」
今度は疑問形ではなく断定で言えた。彼女は暫く何も答えなかった。もはや後には引けず頭が真っ白になった僕は、否定か肯定か、彼女が何かを言う前に、ソファの裏手にある梯子を上り始めた。
キッチンから回って来た彼女が、下から僕を見上げる。
「さぁ、こっち」
ロフトに到達した僕が彼女に向かって言った。上はさすがに残暑の熱気でモワッとしていたけど、過ごせない程ではなかった。
梯子に手を掛けた彼女が不安そうに僕を見上げる。僕は大丈夫、と力強く頷いてみせた。
彼女が上って来る。ロフトは小窓があるくらいで特に目につくものは無い。ディスタンスを保とうと僕が気を遣って奥へ行くと、ようやく彼女が梯子を上りきった。
体育座りになって僕が言う。
「背中合わせなら――」
彼女は頷いて、僕と同じように体育座りになった。そして少しずつ寄り添って、背中をぴったりくっつき合わせた。これなら飛沫感染も接触感染も両方を防げる。
憧れのあの子と背中と背中がくっついている。お互いの心臓の音が聴こえてくるようだ。
突然、窓の外を眺めていた彼女が質問をしてきた。僕は面食らって「え?」と返すので精一杯。
「だってこの壁、スイス漆喰なんでしょ?」
白い壁を触りながら彼女が言った。
「し、漆喰っていうのは、建築材料のことで、日本と西洋とじゃ、成分が違うんだけど――」
咄嗟の僕の説明に、木製サッシの窓から外を眺めている彼女がふむふむと頷く。
「す、スイス漆喰っていうのは、不純物の少ない石灰石が原料で、普通は1400℃の高温で焼くんだけど、スイス漆喰は950℃の低温で1週間かけて焼くんだって。で、そもそもスイスには『バウビオロギー』っていう概念があって――」
そこまで僕が言い掛けると、彼女がハッと振り向いた。「ずいぶん詳しいのね」と驚くような態度で。ところが、僕がスマートフォンで知識のカンニングをしていたことが分かると、彼女は「な~んだ」と落胆するような素振りをみせ、再び背中を向けてしまった。いくら建築学部の僕だって、咄嗟にスイス漆喰が何かなんて、スマートフォンで調べなければ人に説明なんか出来っこない。
僕が弱りながら「ば、バウビオロギーていうのは、健康な住まいを求める新たな学問、建築生物学とか生態学って意味で、 環境意識の高いスイスやドイツなんかで――」と続けても、彼女はもはや興味なし。やがて「別に聞いてない」とそっけなく言って、キッチンのほうへ行ってしまった。
僕もソファから立ち上がって、追うように彼女のほうへ。といっても2メートルの縛りがあるから、僕は食卓で立ち止まって、四人掛けの木製テーブルに立ったまま寄りかかった。
すると彼女が唐突に冷蔵庫を開けた。「なにも入ってないでしょ」と僕が言うと、彼女は「まぁね」と答えてすぐに閉めた。
「いつもなに食べてんの?」
続けざまに彼女が訊いてきた。
「ひ、一人暮らしだから、米を炊いて、チャーハンとか、炒め物が多いかな」
キッチンカウンターの手触りを確かめながら、彼女は「ふ~ん」と僕に返した。
ほとんど対面しているとはいえ、彼女は僕と目を合わせなかった。彼女は天井から下りて来るように設置されている換気扇に興味を示したのか、自分の背丈と比べるような手振りをみせた。
そこから妙な沈黙が流れた。彼女も落ち着きが無かったが、僕だって内心はそわそわしていた。2メートルの距離があるとはいえ、付き合ってもいない若い男女が、家の中で向かい合っているのだ。
「なに考えてるの?」
不意にこちらの考えを見透かしたように彼女が訊いてきた。
「い、いや、別に……」
こちらの曖昧な回答によって再び沈黙が訪れる。僕はこの時、漠然と、彼女と同じことを考えていると思った。「もし、私たちが付き合ったら――」「もし、この家で同棲したら――」「もし――」と。
そういう、荒ぶる気持ちが抑えられなくなった僕は、ええいままよと勇気を振り絞って、彼女に言った。
「ロフトに、行こうか」
「え」
彼女は小さく掠れた声で答えた。
「ロフトに、行こう」
今度は疑問形ではなく断定で言えた。彼女は暫く何も答えなかった。もはや後には引けず頭が真っ白になった僕は、否定か肯定か、彼女が何かを言う前に、ソファの裏手にある梯子を上り始めた。
キッチンから回って来た彼女が、下から僕を見上げる。
「さぁ、こっち」
ロフトに到達した僕が彼女に向かって言った。上はさすがに残暑の熱気でモワッとしていたけど、過ごせない程ではなかった。
梯子に手を掛けた彼女が不安そうに僕を見上げる。僕は大丈夫、と力強く頷いてみせた。
彼女が上って来る。ロフトは小窓があるくらいで特に目につくものは無い。ディスタンスを保とうと僕が気を遣って奥へ行くと、ようやく彼女が梯子を上りきった。
体育座りになって僕が言う。
「背中合わせなら――」
彼女は頷いて、僕と同じように体育座りになった。そして少しずつ寄り添って、背中をぴったりくっつき合わせた。これなら飛沫感染も接触感染も両方を防げる。
憧れのあの子と背中と背中がくっついている。お互いの心臓の音が聴こえてくるようだ。