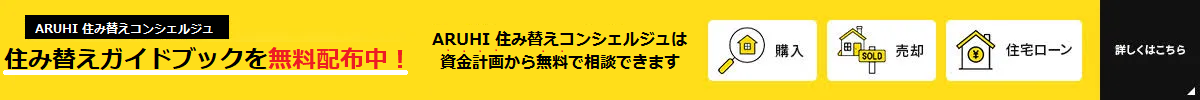「いもう……と?」
「あ、お姉ちゃん。わたし、光。よろしくね」
お姉ちゃんという普段呼ばれ慣れていない言葉に一瞬誰のことかわからなかったが、どうやら本当に目の前に光という名の妹が現れたようだ。
「光ちゃん……。わたし、恵」
「恵姉ちゃんね。なんかして遊ぼ!」
わたしは自分の部屋へ光ちゃんを案内して、おままごとをして遊んだ。これまで家では一人で遊んでいたので、なんだか不思議な気分だ。でも、「お姉ちゃん」という立場も、頼られている感じがしてなんだか居心地がいい。
「おままごと、いつも一人でしてたからなんだか変な感じ」
「そうなんだ。でもこれからは一緒にできるね」
光ちゃんの「これからは」の言葉に胸がキュッとなった。今日のうちには光ちゃんは消さなければいけないのだ。
おままごとを1時間くらいした後、今度はママとお買い物に出かけた。もちろん光ちゃんも一緒に。
やって来たのは大型ショッピングモール。ママが食品を買っている間、わたしと光ちゃんはおもちゃ売り場へ行った。光ちゃんはおもちゃ売り場に着くとクッキングトイのコーナーに向かった。いつものわたしならすぐに大好きなぬいぐるみのコーナーに行くが、今のわたしはお姉ちゃん。光ちゃんが迷子にならないようにずっとそばについていないといけない。
「へぇ、実際にお菓子が作れるおもちゃなんだ。光ちゃんこういうのが好きなんだね」
「うん! だって、これがあったらもっとお姉ちゃんとおままごとできるもん」
「ほんとだね。これがあったらもっとリアルなおままごとになるね」
「でしょでしょ!」
「でも、買ったらパパに怒られるかもね」
「パパ怖いの?」
「怒ったらね。この前パパの部屋にこっそり入ったらバレてね、めちゃくちゃ怒られた。『恵はここに入っちゃいかん!』ってね」
「こわいね」
「それにパパ、わたしと一緒にお風呂に入ってくれたこともないの」
「へぇ、そうなんだ。お姉ちゃんが女の子だからかな? ほら、男の人と女の人、温泉入るときとかわかれてるし」
「そうかなぁ」
そんなことを話していると、楽しくて、あっという間に時間が過ぎ、買い物を終えたママが来た。結局、わたしたちは何も買わずに帰った。
帰宅後、夕食を終えたわたしたちは、一緒にお風呂に入った。
「お姉ちゃん、いつもだれとお風呂に入るの?」
「いつもは一人か、ママかな。パパは一緒に入ってくれないし」
「じゃあ今度から光と入ろうよ」
「うん! 入ろ入ろ!」
あっ、と思う。光ちゃんの提案を喜んで受け入れていたが、すっかり忘れていた。光ちゃんと一緒にいられるのは今日だけなのだ。あともうちょっとでおわかれしなければならない。
「ところで光ちゃんって、いくつなの?」
「んとね、7歳」
「ってことは小学1年生?」
「うん」
「わたしは一個上の小学2年生」
「やった! じゃあ一緒に学校行けるね」
わたしは「うん」とは言えなかった。光ちゃんから未来のことを提示されるたびに、わたしの心はズキリと痛んだ。本当に、このままさよならしてしまうのだろうか。
お風呂から上がると、わたしはママに言った。
「ねぇママ。ほんとに光ちゃん消さなきゃだめ?」
「消すって約束したでしょ?」
「そうだぞ。そろそろだ。消しなさい」
パパが「いもうと」と書かれたボタンをわたしの目の前に差し出す。わたしは渋々それを受け取った。
「パパもママも、恵ちゃんの体に傷がつくのが嫌なの。わかるでしょ?」
「うん……」
そのとき、光ちゃんがやってきた。
「お姉ちゃん。寝るとき一緒に寝ようね」
わたしは一体どうしたらいいのだろうか。
こんなことになるのなら、最初から妹なんて出さなきゃよかった。
「光ちゃん、ごめん!」