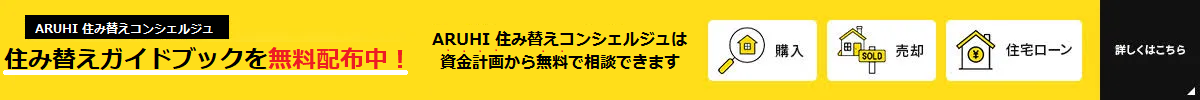すぐ側で声が聞こえて、私は恐る恐る顔を上げる。顔はよく見えないけれど、目の前に誰かがいた。
「どうしたの、転んだの!? 怪我はない?」
しゃがみ込んで、肩で息をしながら私に尋ねる青年は、私を心配してくれているようだった。
「ちょっと疲れて……親切にありがとう」
「そっか、怪我がないならいいんだ。迎えに来たよ、一緒に帰ろう」
「……どちら様?」
青年は言葉に詰まったような顔をして、胸に手を当てた。しばらくの沈黙の後、優しく微笑む。
「さっちゃんが覚えてないなら、初めましてだね。俺は維新っていいます」
ぼんやりと霞む記憶。彼は私を知っているのに、私は彼を思い出せない。
「私、おかしくて……怖いの、不安なの。自分が自分じゃなくなっていくような気がして、戸惑うのよ」
ぐちゃぐちゃな感情をぶつけたって、どうにもならないことくらいわかっている。でも青年は、そんなみっともない私の言葉をただ聞いていた。
「一人にしてごめん、不安にさせてごめんね」
それだけ言って、青年は私の手を取る。
「違うのよ、あなたのせいじゃない。ごめんなさい」
今ならわかる、雪治さんもそうだったもの。
「私、認知症なのね」
青年は俯くように、小さく頷いた。
車を呼んでもらって家まで帰った。見覚えのある家に帰った時、安堵のため息をつく。
「じゃあ、ゆっくり休んでね」
玄関先でそう言われて、私ははっとして振り返る。
「ありがとう。あなた、お名前は何ていうのだっけ?」
ここまで送ってくれた親切な青年の名前がどうしても思い出せない。さっき聞いたはずなのに、情けない話だ。
「俺は藤戸維新、さっちゃんの孫だよ」
その言葉の意味を理解するのに、随分と時間が必要だった。
「私の孫は、まだ高校生のはず」
中学生の頃いじめに遭い、家にも居場所がなくてうちで暮らしていた「しんちゃん」。この前全寮制の高校に受かって、出て行った――心の優しい男の子。
「そうだよね、あれからもう六年も経ってる。だけど俺は、さっちゃんの孫のまま」
「……本当に、しんちゃんなの?」
「うん。中学生の時、不登校だったしんちゃん。あの頃、さっちゃんとゆきじいだけが俺を見放さなかったから、俺は今ここにいる」
「そう、大きくなったのね」
「俺、二人に恩が返せたらってずっと思ってた。それなのにゆきじいは死んじゃって……すごく、後悔してる。大学とか一人暮らしとか、忙しさを理由にしてさ。何でもっと、たくさん会いに行かなかったんだって」
悔しそうに唇を噛む。しかし意を決したように、維新君はまっすぐに私を見た。
「だからさっちゃんのことだけは、絶対に後悔したくないんだ。これからは側にいさせてほしい」
すがるような眼差しに、私は目を伏せた。
「でも、また忘れちゃうかもしれないわ。たくさん迷惑をかけてしまうかも」
彼は私のことを心配して言ってくれているのだろう。でもそれ以上に、私は自分自身を信用できずにいる。
「大丈夫だよ。俺は全部覚えてるから。さっちゃんが忘れちゃったら、その時は『初めまして』からまたやり直そう」
こう見えて社交的になったんだよ、と人懐っこい顔で笑う。自信たっぷりに胸を張る様はなんだかとても頼もしく見えて。
「そうね。私、しんちゃんのこと信じるわ」
「ありがとう。明日もまた来るよ。おやすみ、さっちゃん」
そっと微笑んで、しんちゃん――維新君は去っていく。まるで春風のように私の前に現れて、温かさを残して姿を消した。
「やっと、落ち着いたわね」
仏壇の前で手を合わせる。これから始まる新しい生活にため息をついた時、玄関のチャイムが鳴った。扉を開けると、家の前に青年が立っている。
「こんにちは」
爽やかに挨拶をするその姿は、私の記憶にないけれど――
「こんにちは。初めまして、ではないと思うのだけど……ごめんなさい、上手く思い出せなくて」
どこかで会った誰かな気がした。申し訳ない気持ちで青年を見上げると、嬉しそうに目を細める。
「大丈夫だよ。さっちゃんが忘れても、俺は全部覚えてるから」
『ARUHI アワード2022』10月期の優秀作品一覧は こちら ※ページが切り替わらない場合はオリジナルサイトで再度お試しください