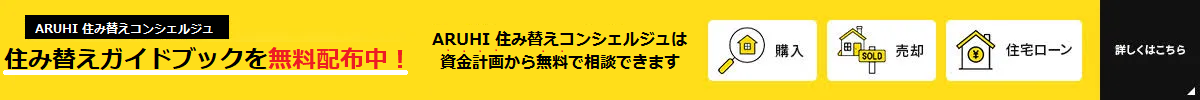また一人辞めてしまう。あの時から私は成長できているのだろうか。役職に相応しい人間なのだろうか。チームをまとめられているのだろうか。部下の気持ちに寄り添えてあげられているのだろうか。
心が弱っているとき、温かいものに触れると涙が出てくる。
今、自分の心がどのくらい弱っているのか分からないが、涙がとめどなく溢れてきた。誰もいないし、少し声を出して泣いてみた。それでも全然平気だった。湯口からゴボゴボと溢れ出てくるお湯の音が私の泣き声をかき消してくれた。
矢木ちゃんは本当に来た。仕事用のパソコンを抱え、大きなリュックを背負って。私の心配をよそに、彼女は山や川の近さに感動し不便さに文句も言わなかった。むしろ私の新しい日常を気に入ってくれているようだった。
「最高ですね」
お湯に浸かりながら矢木ちゃんは言った。数日の滞在のはずが彼女はもう一週間も留まっている。正直、直接面と向かって仕事ができるのは楽だったし、何より話し相手がいることが有難かった。
「私も住んじゃおうかな、こっち」
「え、本当?」
「でも彼氏がなー」
「まぁ、そういうのがあると難しいよね」
「別れようかなー」
「え、そうなの?」
矢木ちゃんは私を翻弄してふふふと笑う。
「高崎さん、知り合いもいないのにこっちに一人で住んで寂しくないんですか?」
「それが意外と平気」
「こうやって直接会えるのは嬉しいけど、離れてても画面越しに会えるし、ご近所さんとも挨拶しあったりできてるし」
「ご近所さんといえば、私あれが食べたいんですけど」
「蕨のキムチ漬け?」
「それです」
「もう食べちゃったよ」
「もらいに行ったりできないですか?どうしても食べたいんです」
もともとフットワークの軽い矢木ちゃんではあるが、ここに来てバグっている。
フミさんの家の灯りはついていた。やっぱりやめようよ、なんて玄関先で私たちがモタモタしているのに気がついてフミさんが玄関を開けてくれた。キムチの蕨漬けが食べたいと伝えると快く中に入れてくれた。
「すみません、なんか押しかけてしまって」
「いいのいいの、たくさんあるから持っていって。なんか飲むかい?」
そう言いながら一升瓶をつかむフミさんに矢木ちゃんは甘えまくった。
「おばあちゃん、一人で暮らしてるんですか?」
矢木ちゃんとフミさんはすっかりほろ酔い状態になっている。
「そうだよ、お父さんが亡くなってもう3年になるからね、一昨年はあんたんとこのおばあちゃんが亡くなっちゃったしね」
「寂しいね」
「そんなことないよ、もうそろそろ私もそっちに行くだろうからさ」
フミさんはケタケタ笑った。
フミさんの家は物が少なくきれいに整えられていた。
「そう言えばあんた、冬もこっちにいるのかい?」
「はい、そのつもりですけど」
「こっちの冬は大変だよ、雪が」
「雪、そうですね」
この辺の雪の事情はなんとなく聞いていた。
「おばあちゃん、どうしてるの?」
「役場の人が除雪しに来てくれるよ、でも人手が足りなくてね。状況によっては冬だけでも郡山にいる息子のとこに行こうかなとも考えてるよ」
「冬をここで過ごすつもりなら、もっとご近所と付き合いしないとダメだよ」
酔っ払っていたフミさんが真剣な顔になる。
「いくら仕事が忙しくっても。声かけあって、助け合っていかないとね」
私は若くして肩書きがついてしまったので、誰かに教えられることが少なくなってしまったような気がしていた。もっとこんな風に色んな人に色んなことを言ってもらいたかった。
家に戻ってからも、矢木ちゃんは蕨のキムチ漬けを肴に飲み続けた。
「そうだ、望月さんに送別会のこと聞かなくちゃ」
「今、起きてるかな?」
「ゲームとかしてるんじゃないですか?」
「起きてたら、ZOOMで話してみようよ」
「え、3人で?のってくれますかね?」
「ダメでもいいから声かけてみようよ」
お湯のおかげで体はまだポカポカしていた。心のストッパーがふやけている。私は望月さんにスラックのメンションを飛ばしてみた。
心が弱っているとき、温かいものに触れると涙が出てくる。
今、自分の心がどのくらい弱っているのか分からないが、涙がとめどなく溢れてきた。誰もいないし、少し声を出して泣いてみた。それでも全然平気だった。湯口からゴボゴボと溢れ出てくるお湯の音が私の泣き声をかき消してくれた。
矢木ちゃんは本当に来た。仕事用のパソコンを抱え、大きなリュックを背負って。私の心配をよそに、彼女は山や川の近さに感動し不便さに文句も言わなかった。むしろ私の新しい日常を気に入ってくれているようだった。
「最高ですね」
お湯に浸かりながら矢木ちゃんは言った。数日の滞在のはずが彼女はもう一週間も留まっている。正直、直接面と向かって仕事ができるのは楽だったし、何より話し相手がいることが有難かった。
「私も住んじゃおうかな、こっち」
「え、本当?」
「でも彼氏がなー」
「まぁ、そういうのがあると難しいよね」
「別れようかなー」
「え、そうなの?」
矢木ちゃんは私を翻弄してふふふと笑う。
「高崎さん、知り合いもいないのにこっちに一人で住んで寂しくないんですか?」
「それが意外と平気」
「こうやって直接会えるのは嬉しいけど、離れてても画面越しに会えるし、ご近所さんとも挨拶しあったりできてるし」
「ご近所さんといえば、私あれが食べたいんですけど」
「蕨のキムチ漬け?」
「それです」
「もう食べちゃったよ」
「もらいに行ったりできないですか?どうしても食べたいんです」
もともとフットワークの軽い矢木ちゃんではあるが、ここに来てバグっている。
フミさんの家の灯りはついていた。やっぱりやめようよ、なんて玄関先で私たちがモタモタしているのに気がついてフミさんが玄関を開けてくれた。キムチの蕨漬けが食べたいと伝えると快く中に入れてくれた。
「すみません、なんか押しかけてしまって」
「いいのいいの、たくさんあるから持っていって。なんか飲むかい?」
そう言いながら一升瓶をつかむフミさんに矢木ちゃんは甘えまくった。
「おばあちゃん、一人で暮らしてるんですか?」
矢木ちゃんとフミさんはすっかりほろ酔い状態になっている。
「そうだよ、お父さんが亡くなってもう3年になるからね、一昨年はあんたんとこのおばあちゃんが亡くなっちゃったしね」
「寂しいね」
「そんなことないよ、もうそろそろ私もそっちに行くだろうからさ」
フミさんはケタケタ笑った。
フミさんの家は物が少なくきれいに整えられていた。
「そう言えばあんた、冬もこっちにいるのかい?」
「はい、そのつもりですけど」
「こっちの冬は大変だよ、雪が」
「雪、そうですね」
この辺の雪の事情はなんとなく聞いていた。
「おばあちゃん、どうしてるの?」
「役場の人が除雪しに来てくれるよ、でも人手が足りなくてね。状況によっては冬だけでも郡山にいる息子のとこに行こうかなとも考えてるよ」
「冬をここで過ごすつもりなら、もっとご近所と付き合いしないとダメだよ」
酔っ払っていたフミさんが真剣な顔になる。
「いくら仕事が忙しくっても。声かけあって、助け合っていかないとね」
私は若くして肩書きがついてしまったので、誰かに教えられることが少なくなってしまったような気がしていた。もっとこんな風に色んな人に色んなことを言ってもらいたかった。
家に戻ってからも、矢木ちゃんは蕨のキムチ漬けを肴に飲み続けた。
「そうだ、望月さんに送別会のこと聞かなくちゃ」
「今、起きてるかな?」
「ゲームとかしてるんじゃないですか?」
「起きてたら、ZOOMで話してみようよ」
「え、3人で?のってくれますかね?」
「ダメでもいいから声かけてみようよ」
お湯のおかげで体はまだポカポカしていた。心のストッパーがふやけている。私は望月さんにスラックのメンションを飛ばしてみた。
『ARUHI アワード2022』9月期の優秀作品一覧は こちら ※ページが切り替わらない場合はオリジナルサイトで再度お試しください