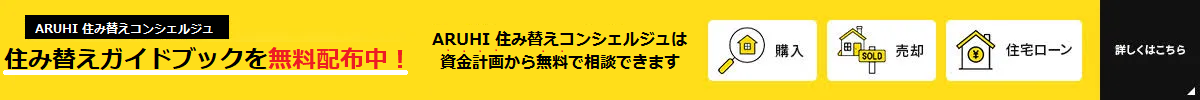中学生になって陸上部に入ると、ミチコは県大会の選抜リレーに向けての朝練で、クウの散歩どころではなくなった。
母も、娘の弁当作りも加わり朝は多忙を極めたが、一言の文句も言わずにクウの散歩を引き継いだ。ゆったりとドリップコーヒーを愉しむ「お母さんの時空」を犠牲にして。
そしてミチコの出かけ際には、洗濯したユニフォームと朝作った弁当を持って、必ず玄関まで見送りに出た。
「行ってらっしゃい。怪我には気を付けるのよ。あんた周りを見てないんだから。」
必ずむっとする余計な一言がつく。わざと母を無視し、一緒に玄関まで出てきたクウにだけ「行ってくるね。クウちゃん」と言って家を飛び出す。
頭の中は、課題になっているバトンパスのことでいっぱいだ。ミチコは走るのは速いが、バトンを受け取るのが下手で、いつも落としてしまうのだ。
時々、クウの散歩がてら母がグランドを見にきた。ミチコはちらと手をふって、すぐに練習に集中した。それでも内心では自分を見にきてくれることが、嬉しかった。
高校2年生になると、それまで一生懸命続けてきた陸上部をやめた。勉強が追い付かず、1学期に赤点をとったことがきっかけだった。この頃のミチコは何もかもがうまくいかず、自信を失っていた。親の一挙一動に腹が立った。
食事中に携帯を見るなと言うくせに、自分は野球中継に夢中で一言も発しない父。最近ふられたのは、自分が口下手でつまらない子だからだ。父が家族サービスを怠っているせいで、自分が口下手になったとミチコは思っていた。
そして、「私は娘と人を比べない」と言いながら、近所の先輩が頭のいい大学に受かったことを羨ましそうに話す母親。赤点をとったことに対する当てつけに聞こえて、憎たらしい。
できるだけ、さっさと食事を済ませてひとりになりたい。そんな、ささくれ立った気持ちを知ってか知らずか、クウは食卓でひとりカリカリとしているミチコに必ずちょっかいをかけた。濡れた鼻をこすりつけて前足でミチコの膝をかく。あんたにあげるのはないよ、と邪険に追いやられるのを知っていても。
就職して家を出ると、ミチコが里帰りするのは年に1回、お正月の時だけになった。
間を埋めるように繰り返される母のお喋り、新聞を広げて顔を見せない寡黙な父、その足元を歩き回るクウ。いつもと変わらない光景だ。
思春期の時は嫌でたまらなかった実家だが、時々こうして帰ると、気楽で落ち着いた。
あ、という誰に向けるでもない声を出して、父が新聞を畳んだかと思うと、今度はテレビの駅伝中継を見始めた。
「東林大学のタナカ!駒川のサトウを追い抜くことができるのか!さあまずはこの2位争い!抜いた!抜きましたぁ!東林大学、そして駒川!さあ、いま!タスキを渡した!東林大学!今、2位で、通過したぁ!」
この小さな逆転劇を眺めながら、ミチコはタスキを渡し終えた走者の、安堵して苦痛から解き放たれる表情に見入った。
「クウがね。」
母がミチコの方を向いて、話し始める。
「最近食が細くなったのよ。もうおじいちゃんなのよね。人間にしたら、80歳くらいだって。ミチコを追い越したと思ったら、私たちも追い越されちゃったわ。犬の時間は、流れるのが速いのよね。」
確かに言われてみれば、茶色の優しい眼差しも、真摯な顔立ちも、インテリふうの垂れ耳も、子供の頃とまるで変わらないのに、薄茶だったはずの体毛は、ほとんどが白髪になっていた。動作も以前よりもゆったりとしている。
その日、クウを連れて、久しぶりに堤防に上がった。
空は鈍色に広がって金属の冷たさを思わせた。
「クウ!よーいドン!」
ミチコはクウに呼び掛けた。だがクウはよたよたと歩くだけで、リードは一向に張らなかった。ミチコも、走る気にはなれなかった。その代わりに、ふたりでよく走った道を眺めた。
空と道の交わるところ。
子供の頃、現実には存在しない場所を目指して夢中で走ったのは、走ることそのものが楽しかったからだ。それがいつのまにか、陸上を始めて、走る目的を知り、自分の役割を知り、それを全うする喜びを知り、そのうちバトンやゴールのないところでは、走ることをしなくなった。
大人になって、ミチコはどこに向かっているのか、何を運んでいるのか、わからなくて辛くなることがある。それらがハッキリわからないと、事を成し遂げることができないという思いからだった。
「昔はたくさん走ったのにね。」
クウの頭を撫でると、クウは申し訳なさそうにミチコを見上げた。
ミチコよりもずっと速い時間を生きているクウは、こんなミチコでも、昔と変わらない子供に見えるのだろうか。あの頃聞こえたクウの心は、もうミチコには聞こえない。
これが、クウと過ごした最後の思い出になった。
結局、ミチコがクウの世話をするという自分の発言の責任を持ったのは、小学生の間だけだった。
クウの面倒を一番みたのは、母だ。クウが一番なついていたのも母で、クウの最期をみとり、クウの死に一番打ちひしがれたのも、母だ。母は、ミチコが連れてきた命の責任を、きちんと負ったのだ。