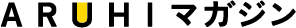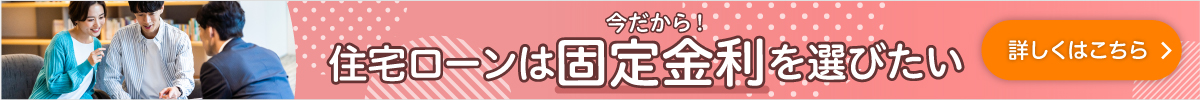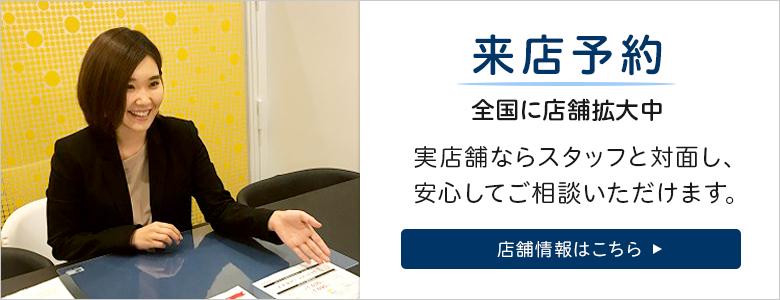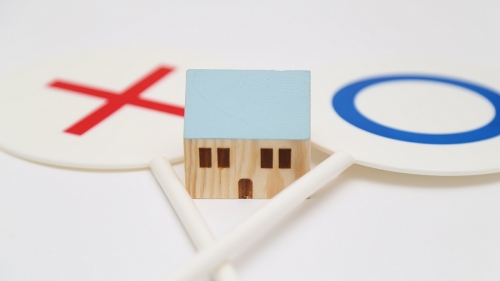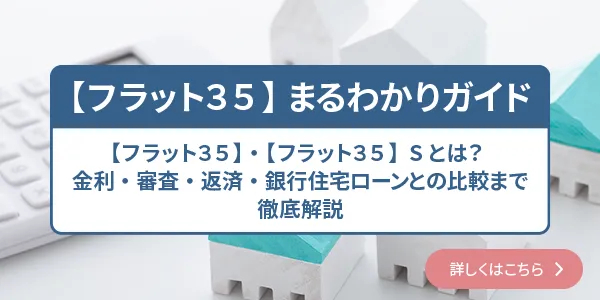住宅ローンの相談を受ける際に良くある質問のひとつに「ボーナス返済はどれくらい利用していいのでしょうか?」というのがあります。過度にボーナス返済に頼った資金計画はリスクがありますが、使い方によっては、大きな助けとなります。上手に活用したいものですね。
ボーナス返済を利用すると毎月の返済額が減るが、総返済額は増える!
ボーナスは、毎月の基本給とは別に支払われる賞与のことで、基本的には基本給×何ヶ月で計算されます。基本給の何ヶ月分と固定されているケースでも、会社の業績によって連動したり、個人の営業成績に応じてボーナスの金額や掛け率が変わったりすることもあります。日本経済団体連合会が2015年10月30日に発表した大手企業の冬のボーナス調査(2015年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況[第1回集計])によると、過去最高となりました。しかし、今後もこの状況が続くとは限りません。ボーナスが下がった場合でもローン返済に支障をきたさないよう、堅実な資金計画を立てたいものですね。
住宅ローンでボーナス返済が利用できる金額は借入金額の40~50%以内という金融機関が一般的です。当然、ボーナス返済を活用することで毎月の返済額を抑えることは可能ですが、その分ボーナス月の返済額が負担となります。必ず、毎月の返済額、ボーナス月の返済額を確認して、その金額を無理なく返済していけるか、チェックをしておきましょう。
| 返済パターン | 毎月返済額 | ボーナス月返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
| ボーナス返済なし | 107,909円 | 107,909円 | 約3,885万円 |
| ボーナス割合20% | 86,327円 | 216,183円 | 約3,887万円 |
| ボーナス割合40% | 64,745円 | 324,458円 | 約3,889万円 |
※ 借入金額 3,000万円、金利1.8%、全期間固定金利型、元利均等方式、返済期間30年、ボーナス月は6月12月と仮定、経費は考慮せず
なお、同じ借入額、同じ金利、同じ期間でローンを組んだ場合、「ボーナス返済なし」と「ボーナス返済あり」では、一般的に総返済額は「ボーナス返済あり」の方が多くなります。
これは、ボーナス返済の元金部分については、6ヶ月間元金返済が据え置かれ、半年間は元金に変化がないため、月払いよりも利息を多く支払うことになるからです。
総返済額がどの程度金額が変わるのかは、借入日、返済日やボーナス月によって異なります。したがって、毎月の家計に余裕かあれば、「ボーナス返済なし」でローンを組み、ボーナスは繰上返済として活用する、という考え方もあります。
ボーナス返済を積極的に活用できるのはどんなケース?
一般的なボーナス返済の考え方は以下の通りです。自分の状況を踏まえたうえで、活用するのかしないのか、どの程度活用するかを考えましょう。
・業績によってボーナス金額の変動が大きいケースでは、ボーナス返済はなるべく利用しない。
・借入金額を増やすことを目的としたボーナス返済は要注意。
・ボーナスでの返済額は、ボーナス支給額の1/3~1/4程度に抑えておく。
・景気や企業の業績が悪くても、ある程度のボーナス水準が確保される人は、積極的に活用してもOK。
・できれば、ボーナス返済の割合は借入金額の20%程度に抑えておく。
・自営業や成功報酬制で毎月の収入が安定しない人は、ボーナス返済を利用することで、毎月の返済分を減らし、余裕がでた月はそれを貯めておけば赤字の月に使うことも可能。
・将来、教育費などで返済に余裕がなくなるかも知れない人は、ボーナス返済分から積極的に繰上返済することで、将来の返済額を減らすことが可能。
ボーナス返済の上手な活用法
自分の収入に合った無理のない返済額に、少しだけプラスαして利用する
ではボーナス返済はどのように活用するのが効果的でしょうか?
まず、自分の収入に適した「長期間無理なく返済できる毎月の返済額」を把握します。そのうえで、その返済額を変えずに、ボーナスの変動があったとしても家計に支障がない金額を少しだけボーナス返済に上乗せする、という考え方です。
具体例でみて見ましょう。
具体例:Aさん夫婦のケース
夫:年収550万円(賞与2回 合計100万円)/ボーナス時期6月と12月
(ボーナスは会社の業績によって変わるが基本給の1.2~1.4ヶ月程度/回)
妻:年収100万円(パート)
<住宅ローンの条件>
借入金額 3,000万円/全期間固定金利型 金利1.8%/元利均等返済
家計から見た無理のない毎月の返済額が約12万円と仮定
※団体信用生命保険や事務手数料などの経費は考慮せず
まず、上記の条件で、毎月返済のみでローンを組むと、以下の通りです。
<毎月返済のみの場合>
| 毎月の返済額 | 116,976円 |
|---|---|
| 返済期間 | 27年間 |
| 総返済額 | 約3,790万円 |
・総返済負担率は、年間返済額1,403,712円÷世帯年収650万円=約21.5%
(一般的に安心とされる目安25%以内に収まっている)
※ 試算と実際の数字とは、異なる場合があります。
ここで、毎月の返済額は変えずに、ボーナス返済月に、無理のないようボーナスの20%分、1回のボーナス返済につき約10万円だけプラスして返済すると、どうなるか見てみましょう。
<3,000万円のうち、375万円分だけ(約13%分)ボーナス返済を活用>
| 毎月の返済額 | 116,221円 |
|---|---|
| ボーナス月の返済額 | 216,139円(毎月の返済額も含めた合計) ⇒ボーナス返済月には、約10万円だけ返済額がプラス |
| 返済期間 | 23年 |
| 総返済額 | 約3,667万円 |
・毎月の返済額は変わらない。
・総返済負担額は、年間返済額1,594,488円÷世帯年収600万円=約24.5%
(一般的に安心とされる目安25%以内に収まっている)
・今後、教育費もかかる点、ボーナスに変動があった場合でも余裕をもたせる点から、ボーナス返済は、年間100万円のうちの20%以内に収めている。
※ 試算と実際の数字とは、異なる場合があります。
ボーナス返済をうまく活用することで、返済期間が4年も短縮でき、期間短縮ができた結果、総返済額を約123万円も減らすことができているのがわかります。
もしボーナスが減ったとしても無理なく返済できる金額はいくらなのか、自分のボーナス状況を考慮し、さまざまなシミュレーションをした上でボーナス返済の活用割合を決めることをオススメします。
ボーナス返済を活用すれば毎月の返済は楽になります。一方で、
・ボーナスは、企業の業績に左右されるため、不確実。
・同じ条件であればボーナス返済を併用した方が毎月返済のみよりも総返済額が多い。
・ボーナスが減って、ボーナス返済をやめる場合に、毎月の返済金額が大幅に増え、家計に支障をきたすことがある。
などのデメリットもあります。過度にボーナス返済に頼った資金計画は危険ですので、ボーナス返済は、目先の負担を減らすためではなく、総返済額を減らす方法として上手に活用しましょう。
(最終更新日:2019.10.05)