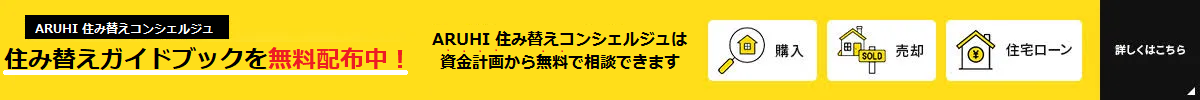そろそろ私のことも記しておく。
15の私へ
あなたが生まれてから明日で15年がたつね。
小さい頃は9月になっただけでそわそわしていたのに、目まぐるしい日々の中でいつのまにか動じなくなっていた。大人になったってことなのかな。
勉強は相変わらずそこそこだけど、この間英語のクラス分けで落ちちゃった。
オーストラリアのときもそうだったけど、いつ成績が必要になるか分からないから、備えておいてね。15歳なんだからしっかりしてよね。
見た目はあんまり成長していないけど、中身がすごく変わったよ。
14歳ってやっぱり大変だったけど、発見に満ちていた。
色んなものの見方、考え方を知ったり、世界のことについて考えるようになった。
学校と家だけの世界の外に目を向けるようになった。
もっと強くなって、その強さを他の人に分けられるような人になってほしい。
5
落選した私がどうやって教室まで帰ったのかは覚えていない。ただ、同じクラスの子に「落ちちゃった」と笑顔で話したことは想像ができる。私にはつらい時でも無理矢理笑顔で話す癖がある。「どんなときでも笑顔」と言えば聞こえはいいが、辛く、悲しく、苦しいことが相手に伝わらないことはやるせない。要するに、笑顔の仮面が顔にへばりついて剥がれないのだ。表情筋が「心配をかけてはならない」とプレッシャーを感じ、一人芝居をするのだ。表面では笑っているものの、心の中では限界だった。成績順のはずが急遽運次第の賭けになった理不尽なこと、様々なことを我慢してオーストラリアへの切符を夢見た日々を思い出しているうちに、気づいたら5時間目が始まっていた。一時休戦となっていた風邪と私の免疫の闘争が再び火蓋を切った。心にも体にも負担がたまった私は手を挙げ、保健室へ向かった。授業中に体調不良者が出た場合、保健委員が付き添わなければならない決まりなので、保健委員の子と共に教室をでた。私のオーストラリアのゴタゴタに巻き込んでしまった彼女にとても申し訳なく思った。保健室で熱を測ると、微熱があった。私にとっては熱があろうとなかろうとどうでもよかった。ただ、保健室の先生は大事を取って早退しなさいと言った。太陽がまださんさんと照り付ける中、5月の昼を一人で味わった。家につき、学校に無事家についたことを報告し、仕事中の母の携帯へも同様にした。
「早退した」「くじ引きダメだった」
「残念だったね。それで早退したの?」
「うん」
「じゃあ気が済むまで休んでいいよ」「夕食、外に食べに行く?」
「どうしよう」
「どうする」
「そうする」
「わかった」
母からの返信をもらったとき、私はどうしようもなくいたたまれなかった。他の人から見れば「たかが海外研修」という出来事に一喜一憂している自分が情けなく思えた。「気が済むまで休んでいいよ」と言ってくれた母に、こんな娘のことまで考えてくれてありがたいのと申し訳ないのが混ざった気持ちが一気に私の心を染めた。感情の整理が追いつかず、出てきたのは涙だった。もっと強くなろう、そう心に誓いを立てた5月12日だった。
6
私がいまこの備忘録を書いているのは例の「オーストラリア事件」で母が連れてきてくれたレストランだ。我が家は外食をめったにせず、私が中学生になってからは一度もない。
久しぶりの肉親との外食に少し緊張し、店員を呼ぶボタンを押す指が少しこわばった。そのとき注文したのはドリアだった。前に友だちと食べたときとはどこか味が違っていた。別のおいしさがそこにあった気がした。そして今もドリアを食べている。しかしあのときと違うのはドリンクバーを頼んでいる、という点だ。傷ついた心に炭酸飲料は刺激がありすぎるため、あのときは注文しなかったドリンクバーと再会を果たし、14最後の日に祝杯を挙げている。ふと大声がしたため、声の方向を見るとその主は前の席の男の子のようだ。男の子とお母さんは何やら口論をしている。口論と言ってもどこかの国の大人がするような自分の正当性を主張するための諍いではなく、男の子が悪戯をし、それを母親が注意をしている、という光景だった。男の子は叱られても悪びれるそぶりも見せず、同じことを繰り返し、また一喝されるのだった。