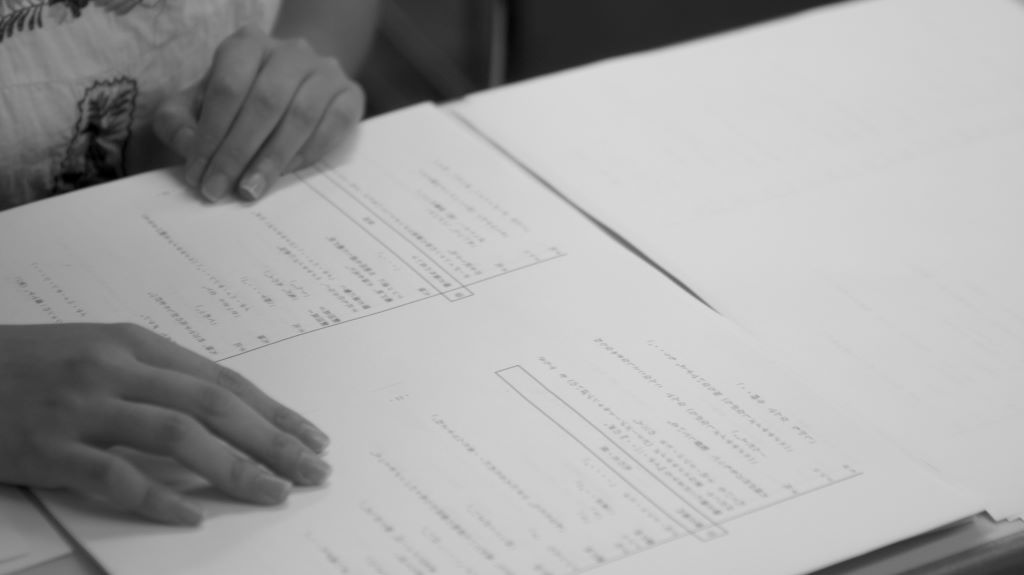太陽は鮮やかな夕焼けを残して山の向こうに沈み、ユキは家に帰った。机の上に残されたのは、スマホとケースに入った卒アルと、未完成の台本だけだ。私は台本を裏返して、最後のセリフを指でなぞった。
―どうせ結果なんて出ないんだから
―目の前のことに、必死
小学校のピアノ教室、中学校のバド部、高校の演劇部。結果を出すために時間をかけるのが嫌で、ダメだと分かればすぐに物事を諦めるような―そんな人間が唯一演劇部だけを続けられたのはきっと、「目の前のことに必死」になれる瞬間がそこにはあったからだ。そして台本を書いていた時間の中に、多くの時間をかけていることすら忘れてしまうような「一瞬」は確かにあった筈なのだ。
「終わり方、どうしようかな」
凄いやつ、とかいう見えない背中を追いかけていた当時の私に、物語の結末なんて見えなかっただろう。だから今度は日常の中に目を凝らし、そこで見つけた何かを拾い上げていけば、結末の輪郭が見えてくる気がした。ユキも三浦も道重さんも、そうやって自分の輪郭を作っている。
ピコン、という通知音がして、画面上方に小さなウィンドウが表示された。どうやら昼間の投稿に返事が来たようだった。
『お久しぶりです、先輩。本来なら三年生は地区大会前に引退しますが、僕は進路が決まっているので、照明として舞台に関わっています』
『良かったら是非見に来てください』
立て続けにメッセージを受け取る。背中はヒヤリとしなかった。そしてまた新たに浮かび上がったウィンドウを見て―
『差し入れは、台本の続きでお願いします』
―やってくれたな
知らず、笑みがこぼれた。あの汚い部室から台本のコピーを見つけるなんて、彼らもものを見つけるのが上手い。
『差し入れ持って観に行くよ』
私の親指が、スクリーンの上を軽やかに踊る。私の生活を、顔も知らない誰かが覗く。それで良かった。今はただ、二十歳になったことを皆に知らせたい気分なのだ。
「ARUHIアワード」11月期の優秀作品一覧はこちら
「ARUHIアワード」10月期の優秀作品一覧はこちら
「ARUHIアワード」9月期の優秀作品一覧はこちら
※ページが切り替わらない場合はオリジナルサイトで再度お試しください