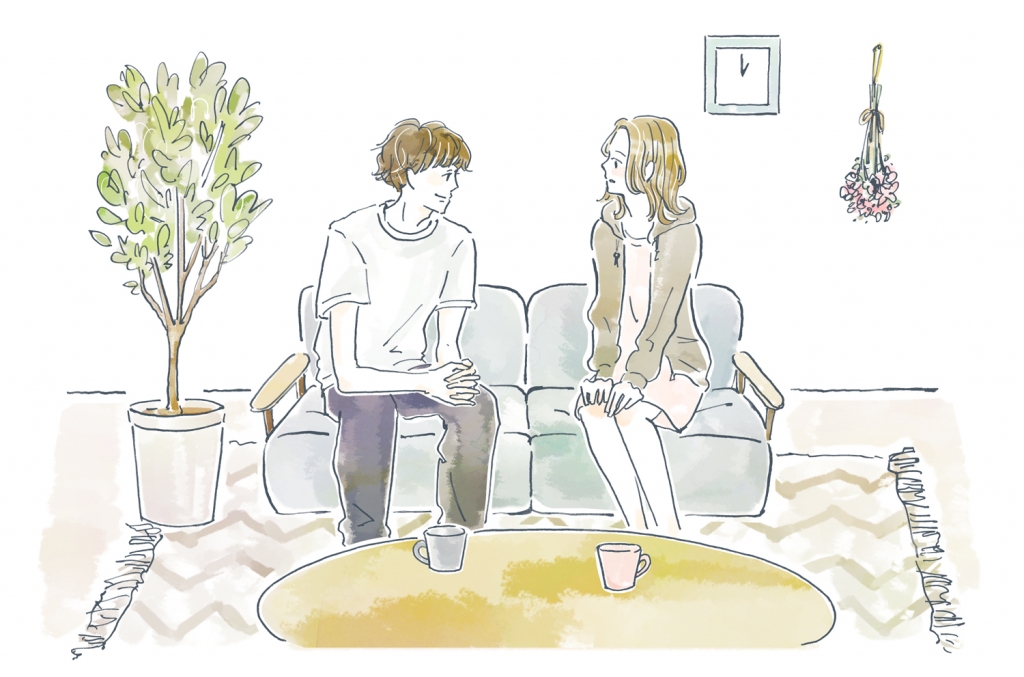「そろそろ約束の一年が経つわけですが」
彼がそう言い始めた時、時刻は13時で、わたしたちはソファに座ってくつろいでいた。いつも通りの日曜日。いつも通り彼はコーヒーを、わたしはダージリンティーを。お揃いのマグカップは、この家に引っ越してきた時、近所の雑貨屋で買ったものだ。日曜日は、こんなふうに昼過ぎまでゆっくり過ごすのがいつの間にか定番になっていた。365日丁寧に重ねてきた、穏やかで愛おしい日々。
ちょうど一年前の5月1日。
わたしたちは二つのバラバラな場所から、一つの家に引っ越してきた。あの日は予定していたベッドのマットレスが届かず、かたい床にダンボールを敷いて、その上にさらに冬物のコートとバスタオルやマフラーなんかをたっぷり敷いた。それでも床はかたくて冷たくて。5月にしては珍しいほど寒かったその日、二人で荒野に取り残された動物のようにしっかりくっついて眠った。
二人だったから乗り越えることができたけれど、きっと一人だったら泣いていたと思う。そのとき、そう彼に告げると、彼は「これからは二人だから泣かずに済むね」と笑っていた。
「……そうだね、あの日から一年経つね」
約束、を忘れた日など1日もない。きっと彼も覚えているだろうとは思っていたけれど、彼が言いだしてくれることの嬉しさ。
本当は朝からずっとそわそわしていた。眠る前から「明日が一年だ」と思い、歯磨きをした後も、パンを食べているときも、なにかを言い出すかもしれない彼をじっと見つめていた。計画的な彼らしく、わたしが待ちくたびれるよりも早く、口を開いてくれた。こういうところも彼らしくて、安心する。
「ね。そういうわけで」
「はい」
彼は身体をこちらに向けて、目をしっかりと見つめる。
答えを言う準備はできている。
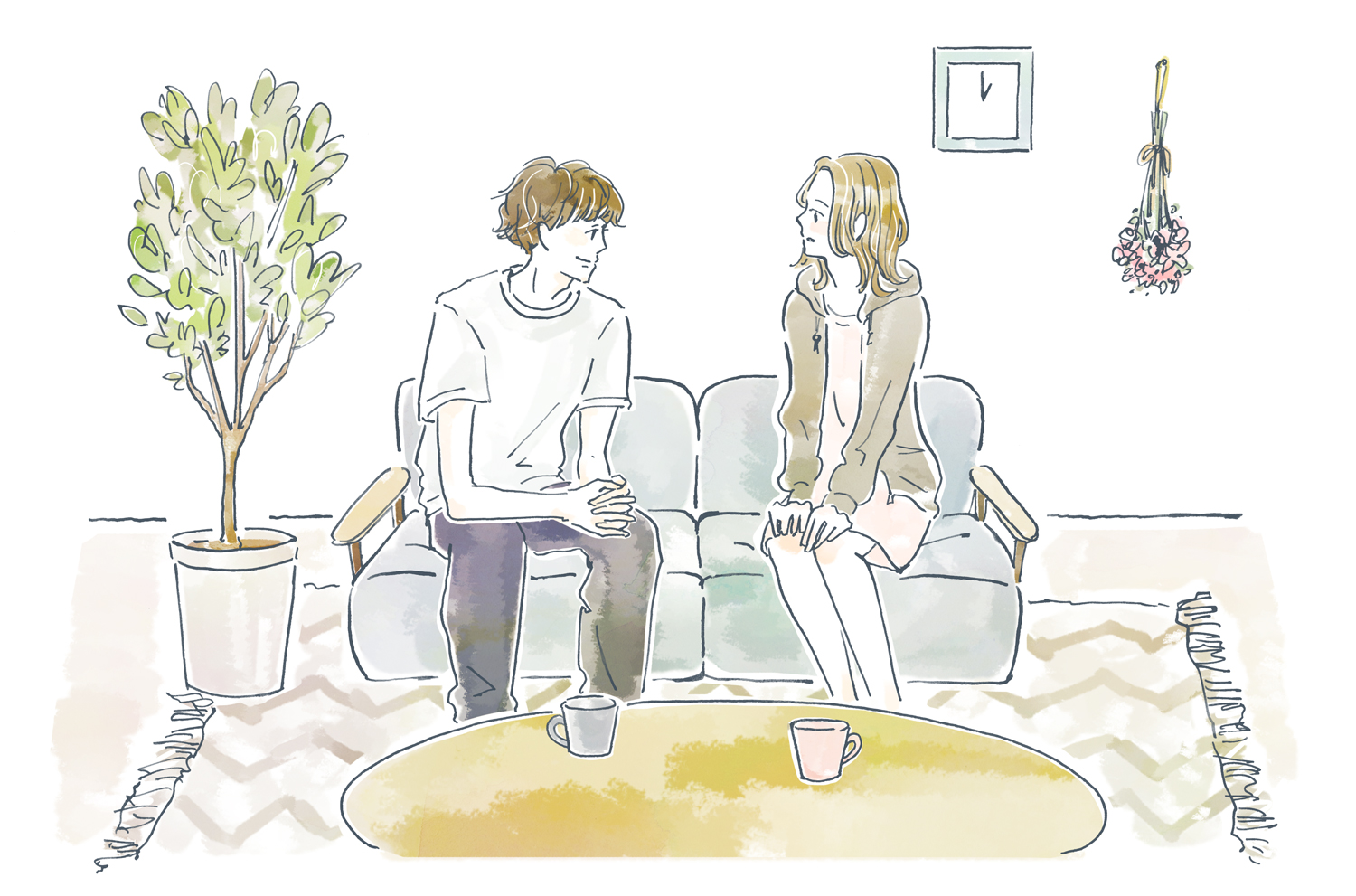
「結婚しようか」
「……する!」
昔は、プロポーズというのはサプライズでするものだと思っていた。男の人が「今だ」と思うタイミングで、高級ディナーや指輪を用意してプロポーズする。女の人は感動と驚きで、ほぼ半泣きになりながら「うん」と答える。そういうものだと思っていた。ドラマや映画では、そういうタイプのプロポーズしか見たことがなかったから。
でもわたしたちは違う。お互いがもうこの日を知っていて、あとは言い出すタイミングと、答えを言えばいいだけだった。
というのも、実は一年前、かたい床の上で一度目のプロポーズを受けたからだ。眠るまえ、耳元で「結婚して欲しい。すぐじゃない。一年後、もう一度プロポーズするから、そのときに」と。
慎重派の私を気遣って、彼は「君が一年間、僕が結婚する相手にふさわしいかを見極めてくれていいから」と言ってくれた。嬉しくて嬉しくて仕方なかったくせに、私はかわいげもなく「一年後って、きっかり一年後? それともだいたい一年後?」なんて聞いて、二人で大笑いしたのだった。「きっかり一年後、5月1日だよ」「わかった、5月1日ね」。
そして一年後の今日、彼は約束を守ってくれた……というわけだ。当然わたしたちは、何の迷いもなく結婚を決めた。やわらかなソファの上で。指輪も、高級なディナーも、サプライズもない。でもわたしたちが積み重ねてきた一年間を象徴するような、ゆるやかなのに“確か”で、優しいプロポーズだった。
「一年経っても、気持ちは変わらなかった?」
うん、と言ってくれるだろうとわかっていて、質問する。
「うん。むしろ、一年が長く感じるほどだった」
「どういう意味?」
「なんどもなんども、もうプロポーズしたい、はやく家族になりたいって思ったから」
かわいすぎる返答を聞いた途端、鼻の奥がツンと痛くなった。痛みがじんわり目の方へ上がってきて、目の前の彼がじわっとぼやけた。実を言えば、わたしだって同じことを思っていた。一年といわず今すぐにでも、となんども思った。焦っていたわけではない。好きの気持ちが抑えきれなくなって、この先もずっと一緒にいたいという思いが溢れて、何度「結婚して」と抱きつきそうになったことか。でも我慢し続けてきたのだ。一年後という、彼との約束のために。その時間、彼も同じことを考えていたなんて、あまりに幸せすぎる。
「よかった」と安堵の表情で微笑んだ彼は、スッと立ち上がり、声を漏らしながら大きく伸びをした。ちらりと見える腰。腰まわりのなだらかなくびれが、わたしをいつだってときめかせる。
見とれていると、身体をキュッとひねって彼が話を続けた。
「あまりいっぺんに話すのは良くないかなとは思ったんだけど」
「…え、なに?」
「引っ越さない?」
そう話す彼の顔は、いつもよりちょっと明るい。何か嬉しいことを企んでいるときの顔だ。
「あ、そっか。4月の異動で職場まで遠くなっちゃったもんね」
「あ、そうじゃなくて」
「違うの?」
「籍を入れてからでいいし、式が落ち着いてからでもいいんだけど」
「うん」
「買いたいな、と思って。家を」
「えっ」
曰く、この先もずっと一緒にいるのだから、そのほうがいいのだという。そういえば、彼のお兄さんが最近家を買うことにしたらしいから、色々と話を聞いていたのかもしれない。彼の話は、地に足のついた家族計画で私は驚いてしまった。プロポーズの直後に、家を買う話……か。なんて現実的な時間なんだ。
結婚は、一気に甘やかさを奪うと言う。
「恋人同士のようにはいられないよ」と脅しを聞かされたことがなんどもある。今になってわかる。たしかに、甘やかな時間はこの先どんどん失われていくだろう。初デートの時のように映画のチケットをあらかじめ用意してくれたり、おしゃれなディナーをサプライズで用意してくれたりしないだろう。会えなくてさみしい夜も、デートの約束に浮き足立つ夜もなくなってしまう。もしかしたら、結婚をした安心感から、ヤキモチも妬いてもらえないかもしれない。
たしかにそれは少しさみしいことでもあるけれど、でも。
日常のあれこれを一人ではなく二人で考えていけるという喜びがある。この先、何があっても一人ではないという安心も。わたしの家は、彼の家でもある。家を決めるのも、一人ではなく二人で。人生設計をするのも、一人ではなく二人で。甘やかさはなくても、そこには幸せがある。穏やかで頼もしく、今よりもずっと強くなれるような幸せが。
「ねえ、どんな家がいい? 教えてほしいな」
彼は小さな子どもを促す時のような口調で話してくる。この口調が、大好きだ。
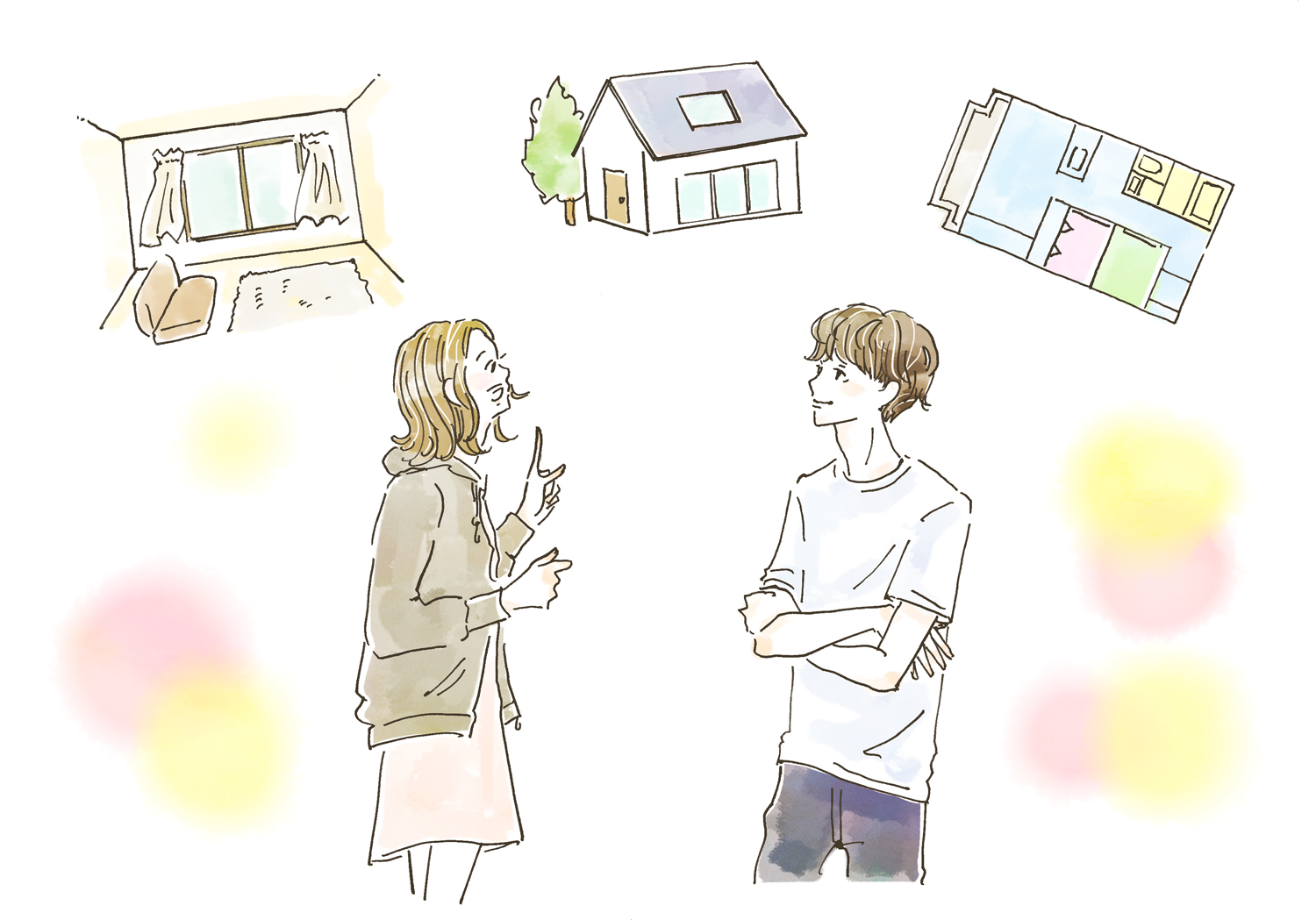
「そうだなぁ。窓が大きくて、天窓があって」
わたしはひとつひとつ、理想を思い描く。今の家も好きだけれど、この先も住むのだとしたら。
「リビングが15畳以上あって、子どもができるかもしれないから2LDK以上で。床暖房が付いていて」
「うん」
「そこであなたとくっついて座れる大きなソファがあって」
「うん」
「それから、わたしたちがいつものように笑っている家」
「なにそれ(笑)笑っているのは、当然でしょ?」
「ううん。“当然”なんかじゃない」
「そう?」
「わたしたちが笑っていられるのは、あなたのおかげだと思う」
「そう? きみがいつもおかしなことをするからじゃない?」
「ちがう! あなたが変な冗談ばかり言うからよ」
二人して、褒め合っているのかけなしあっているのかわからない話をして、目を合わせてくすくす笑った。「あとは……」、そう続きを言いながら立ち上がって、彼の身体に手を回すと、ゆっくりと抱きしめてくれた。日々を重ねてきた部屋で、まだ恋人同士の二人はしっかりと抱き合って、身体の先まで幸せを感じる。
「あとは、なんでもいい。二人で決めるなら、なんでも」
この家は、いい家だった。1LDKの小さな家。二人で初めて住んだ家。少しの喧嘩と、少しの話し合いと、たくさんの幸せを作った家。この思い出を二人で持ったまま、二人で新しい家に行くのはとても贅沢な気がした。しかも、二人で決めた、二人で買った家で。
「この先も、ずっと笑っていたいね」
「そうしようね」
たとえ結婚が二人の甘やかさを奪っても、たとえ子どもが二人を“おとうさん”と“おかあさん”にしても、わたしたちの幸せは形を変えながら続いていくはずだ。
素足に触れる床の感触。後ろのカーテンから透ける光。彼の大きくて細い指の感触と温もり。Tシャツについた柔軟剤の匂い。
この1日を、私はこの先もずっと忘れないだろう。この日をきっかけに、わたしたちは家族になる。そういう幸せな未来に続く「ある日」が、誰にでもあるのだと思うと、世界を今よりも愛せる気がする。
▼第1話・第2話はこちら
【夏生さえり小説<1>】理想の家探し「海の近くで暮らしたい」
【夏生さえり小説<2>】理想の家探し「年上ぶりたい夫、妻ぶりたい妻」
著者:夏生さえり
 フリーライター。出版社、Web編集者勤務を経て、2016年4月に独立。Twitterの恋愛妄想ツイートが話題となり、フォロワー数は合計18万人を突破(月間閲覧数1500万回以上)。難しいことをやわらかくすること、人の心の動きを描きだすこと、何気ない日常にストーリーを生み出すことが得意。好きなものは、雨とやわらかい言葉とあたたかな紅茶。著書に『今日は、自分を甘やかす』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。共著に『今年の春は、とびきり素敵な春にするってさっき決めた』(PHP研究所)。『口説き文句は決めている』(クラーケン)。Twitter:@N908Sa
フリーライター。出版社、Web編集者勤務を経て、2016年4月に独立。Twitterの恋愛妄想ツイートが話題となり、フォロワー数は合計18万人を突破(月間閲覧数1500万回以上)。難しいことをやわらかくすること、人の心の動きを描きだすこと、何気ない日常にストーリーを生み出すことが得意。好きなものは、雨とやわらかい言葉とあたたかな紅茶。著書に『今日は、自分を甘やかす』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。共著に『今年の春は、とびきり素敵な春にするってさっき決めた』(PHP研究所)。『口説き文句は決めている』(クラーケン)。Twitter:@N908Sa